材量
- 大和芋 ・・・180g
- 卵 ・・・1個
- めんつゆ ・・・小さじ2(3倍濃縮タイプ)
- しょうゆ ・・・小さじ1
- 酢 ・・・小さじ1
- 焼き海苔 ・・・適量
- 麦ご飯 ・・・茶碗2膳分
作り方
- 大和芋はピーラーで皮をむいて、おろし金ですりおろします。
- おろした大和芋をすり鉢に入れ、すりこぎですり混ぜ、卵、酢、めんつゆ、しょうゆを加えすりこぎでよくすります。
- 器に麦ご飯を盛り、とろろ汁をかけて好みで焼き海苔を刻んで散らします。
キッチンメモ
定番のとろろかけご飯の紹介です。
すり鉢でスリスリしている間においしくなるような気がします。
すり下ろしてからすり鉢でするとなめらかな【とろろ】になります。
フードプロセッサーに山芋すりの刃が付属しているものもあるので。
大量に作りたいときは便利です。
道具類は水でサッと濡らしてから使います。
山芋や大和芋がなければ、長芋で。
山芋や大和芋の方が、水分が少なく粘りが強いです。
動画でマジカルキッチンレシピ
動画でレシピが見られます。
マジカルキッチン季節の特集
ネバネバ粘り強いので、受験生は「ネバーギブアップ」見習いたいもの。
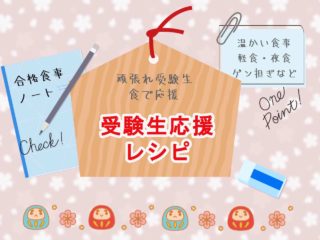
ちなみに6月16日は語呂合わせで麦とろご飯の日。
手軽にめんつゆ利用して作る、ネバネバのとろろ汁に麦ご飯。
プチプチした麦がとてもあいます。
もちろん麦ご飯でなく普通のご飯でも。
麺つゆだけだと甘いので、醤油も加えることがポイントです。
酢は小さじ1程度なら、酸味を感じません。
酢には減塩効果あり。
味の濃さは、醤油で調節を。
お昼ごはんにぴったりのとろろかけご飯。
夏にはわさびを入れるのもいいですよ。
焼き海苔の他、青のりをふっても。
山芋長芋大和芋、手につくとかゆみが出るときありますね。
その場合は酢水で洗うといいそうです。
麦ご飯の炊き方
白米か玄米の中に押し麦を入れて炊きます。(詳しくは、押麦のパッケージ裏に表示が。)
炊飯器の水位の目盛りより、やや多めに水加減します。(麦は、お米より水分を吸うそうです)
いつも通り炊きあげます。
お好みで、麦の割合は変えて。始めから、あまり多く入れると食べにくいかもしれません。
おすすめの麦の割合は。
米の1~2割です。(お米3合に麦50gで1割の割合)
米のカップ1合=180mlに米2合半、麦半合程度。
とろろと一緒に食べる時はもう少し麦の割合を多くしても。
麦は食物繊維があるので、ヘルシーです。
麦とろご飯の作り方を写真で説明

すり鉢、すりこ木、おろし金を用意します。
道具類はサッと水で濡らしておきます。

押し麦です。麦ごはんにする場合は麦を用意。

お米より大きな平たい粒です。
おろし金で下ろした長芋をすり鉢で、なめらかにすります。

ピーラーで山芋の皮をむきます。
おろし金ですりおろします。

すり鉢とすりこ木ですります。
さらに卵、調味料を加えて混ざり合うまですります。
麦とろご飯のレトロな話
麦とろご飯ってなんだか懐かしいご飯もの。
昭和レトロどころか、江戸時代の弥次さん喜多さんでお馴染みの『東海道中膝栗毛』
にも丸子名物として麦とろが登場します。
昭和レトロな食卓にもとろろかけご飯は、お似合いです。
すり鉢を使うこともノスタルジック。
お母さんのお手伝いとして、すり鉢とすりこ木でとろろをすりすりした
思い出がある昭和キッズもいらっしゃるかもしれません。
さて、麦ご飯ですが。
昭和も戦後から戦後そして高度経済成長期を過ぎて時代はすすみます。
家庭で麦ご飯、玄米ご飯が食べられることは減りました。
麦とろも、白米にとろろをかけたとろろかけご飯が多かったかもしれませんね。
現在では麦の健康効果が見直され、麦入りのご飯も人気があります。





