材料
- 柚子 ・・・600g
- 砂糖 ・・・400g(柚子の60~70%くらいが目安)
- 水 ・・・ひたひたの量
作り方
- (果汁を絞り、袋を出す)柚子は丁寧に洗い、汚れた部分があれば包丁で切り落とします。横半分に切り、果汁を絞り茶こしなどで液をこします。半分に切り、袋(薄皮)と皮をわけ、袋はざく切りにします。種は捨てずにそのままお茶パックに入れます。(鍋に種、袋、果汁を入れておく)
- (皮を切る)皮を包丁で薄切りにし(できるだけ細くすると口当たりがよい)、ヘタは切り落とします。ボウルにたっぷりの水を入れ皮をさらします。2~3回ほど水をかえ苦味を抜きます。(2~3時間つける)最後は流水でざっと洗いザルに上げ水気を切ります。
- (皮を柔らかく煮る)種と袋を入れた鍋に皮を入れ、水をひたひた程度の量加え、強めの火にかけます。(木べらで時々底からかき混ぜながら)煮立ったら強めの中火にし、皮を柔らかく煮ます。(圧力鍋の場合2分加圧し、自然に圧が下がるまで待つ)
- (砂糖を加えて煮る)皮が柔らかくなれば(皮が爪でスッと切れる柔らかさになるまで)、砂糖を3回に分けて加え(間隔をあけ)時々木べらで底からかき混ぜとろみがつくまで中火で煮ます。
- (保存)殺菌した瓶に詰めて保存します。作りたてよりも翌日の方が味がなじみます。
キッチンメモ
ゆずで作ったジャムは、色は黄金、香りはさわやか。
和を感じる上品な味わい。
オレンジマーマレードしか食べたことがない人は驚くはず。
こんなマーマレードがあったのかと。
柚子マーマレードの砂糖の割合は60~70%
柚子は酸味が強いので、50%より上にしています。
他の甘い柑橘、たとえば金柑マーマレードの場合
砂糖の割合の目安40%で作っています。
300ml瓶で2本と2/3くらいできました。
マーマレード独特のほろ苦さ。
この柚子マーマレードの場合、ほどほどちょうどいいほろ苦さです。
ほろ苦いマーマレードにしたい場合は、水にさらす時間を短めにします。
逆に苦味をもっと取り除きたい場合は、水にさらす時間を長めにする。
または湯でこぼします。
作ってすぐよりも、一日置いたほうが、味がなじんで苦味も薄く、全体的に濃厚になります。
皮の下処理について
皮を水にさらして苦味を抜きます。
水を3回かえて2~3時間つけています。

柚子はトロミがつきやすいので、煮詰めすぎに注意。
この火を止めるタイミングが難しいんですよね。
緩めになったものは、フルーツソース風にヨーグルトや柚子茶のかわりにしてます。
柚子マーマレードはかぶや大根の甘酢漬け等、料理にも使いやすいです。
柚子マーマレードのレシピ動画
レシピ動画、youtubeにて公開中
youtubeマジカルキッチンチャンネル
チャンネル登録、動画へのいいね!
応援ありがとうございます。
柚子マーマレードの作り方を写真で説明

柚子と砂糖、水を加えて煮ます。

柚子は横半分に切り、果汁を絞ります。
レモン絞り器を使いました。
手でギュッと絞っても絞れます。
絞った後の皮から袋(薄皮)を取り外します。
果汁はザルでこして種を取り除きお茶パックに入れます。
立派な種!

固そうな白いヒモ(ヒゲ)のような部分は取りのぞいておきます。

鍋に種、袋、果汁を入れたところ。

皮は細く切り水にさらします。

この段階では砂糖を入れずに煮ます。
皮、種、果汁、袋、水を入れて煮ます。
圧力鍋の場合は加圧します。

皮を煮た後、取り出して柔らかくなったかチェック。
爪でスッと切れるくらいの柔らかさに。
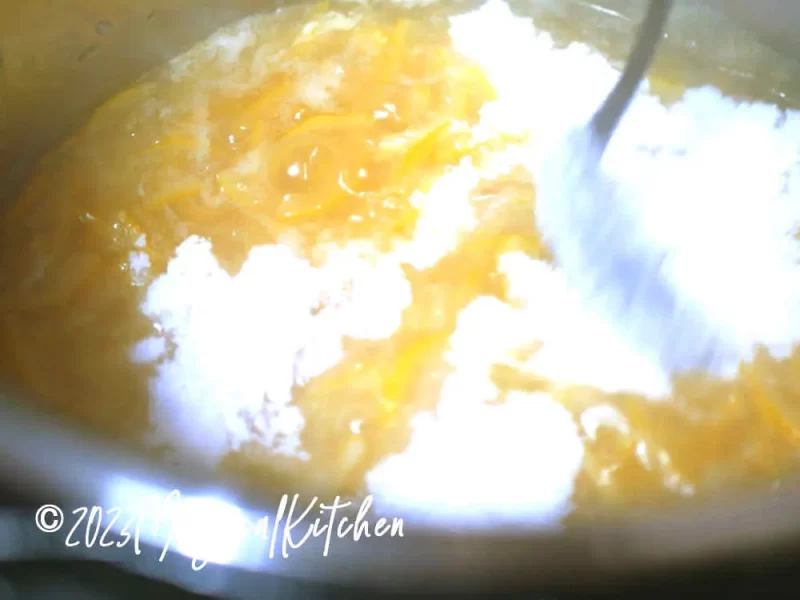
砂糖を加えて煮つめていきます。
始めはサラサラしてますが、徐々にとろみがついてきます。
瓶の煮沸消毒に時間がかかるので、煮込み始めたら煮沸消毒もスタート。
熱い瓶に熱いジャムを詰めるように時間を調節します。
瓶に詰める、保存方法はマジカルキッチンTipsコーナーにて

マジカルキッチンお菓子作りのTips、今回はジャム作りについて。作り方、材料選び。煮沸消毒した瓶に熱いジャムを詰めて保存する方法まで紹介します。
容器・消毒・保存などマジカルキッチン、ジャム保存食について役立ちTips
ジャムや保存食作りで、迷ったり悩むのが容器の選び方、瓶の消毒、保存方法。
特に初めて作るときは、悩みが多いですよね。
具体的な方法や役立ち情報を記事にまとめています。

マジカルキッチンお菓子、料理のTips今回は保存食や常備菜、ジャム、シロップ等を保存する注意点。煮沸消毒、アルコールでの殺菌について

気をつける点、実際に使って分かった点など取り上げます。

マジカルキッチンお菓子作りのTips、今回はジャム作りについて。作り方、材料選び。煮沸消毒した瓶に熱いジャムを詰めて保存する方法まで紹介します。

食べきれないジャム、マーマレード、料理にお菓子に大活用。料理は隠し味に、焼き菓子、デザートに。
煮る際の注意点
はじめにまず、皮を柔らかく煮ます。
この時は、砂糖なし。
皮、種、果汁、袋、水を鍋に入れて砂糖を入れずに煮ます。
砂糖を早く入れると、皮が柔らかくなりにくいのです。
柔らかく煮えれば、次は砂糖を加えて煮ます。
砂糖を加える時は3回に分けて加えます。
1回目入れたら、しばらく煮て2回目を加え、もう少し煮てから3回目。
間隔をあけて加えます。
砂糖を分けて加える理由。
一度に入れるより分けて入れた方が皮が硬くなりにくいためです。
また、一度にたくさんの砂糖を加えると、ジャムが焦げたり固まりすぎたりするリスクが高まりますが、分けて加えるとその心配が減ります。
ジャムの濃度や粘度を確認しながら作ることができるので、自分好みの仕上がりにすることが可能です。
柚子の洗い方

柚子を洗う際は、1個ずつ水洗いします。(アクリルたわしを使ってます)
汚れが気になる場合は、塩をこすりつけて洗う方法もあります。
農薬が気になる方は、湯に1分程度つけてから洗います。
柚子の皮にはビタミンCやクエン酸などの栄養素が豊富に含まれているので、料理に活用するのがおすすめです。
黒っぽい点がある柚子について
柚子の病気で、何種類かあります。
すす病、サビダニ、黒点病
見た目は悪いけど食べても人間に害はありません。
ジャムにする場合、黒い部分が気になる大きさなら、切り取って使います。
ジャムの煮あがり、火を止めるタイミングが分かりにくい場合
ゆずマーマレードが煮上がったかどうかの見極め。
汁がチャパチャパした状態から、とろっとしてきます。
それが、とろんとろんとなります。
色が黄色から少しオレンジがかった色になる頃です。
冷えるとさらに固まるので、ドロッとするくらいに詰めると煮詰めすぎになります。
この段階で完成品のジャムの濃度にしていまうと、冷えた時に固くなります。
煮詰めすぎた場合は水を加えます。
煮詰め具合が、分かりずらい場合は、コップテストやお皿にたらして固まり具合を確認します。
コップテスト
コップに冷水を注ぎ、ジャムをスプーンでほんの少したらして、落ちる様子を観察する
上の方でパッと散ればまだ煮たりない。
上の方で散らずにコップの底まで落ちればOK
小皿で確認
冷蔵庫で冷やした小皿に少量のジャムをつけます。
冷蔵庫へ少し入れて冷やします。
取り出し小皿を斜めに傾け、状態を確認します。
ジャム状のトロミがついていればOK
皿やジャムを冷やすことで、冷えた時のジャムの固まり具合がわかります。
柚子ジャム作りが簡単楽しい理由
柑橘系のジャムが好きで、レモンや伊予柑などでもよく作ります。
なかでも柚子ジャムはお気に入り。
その理由は、まず味も香りも上品なこと。
華やかなオレンジとは違う上品さがあるんですよ。
作る面でも、作りやすく、失敗が少ない点がいい。
ペクチンが多く、毎回面白いようにとろみがつくんですよ。
もう皮切ったり、種を触った時点でペクチンが多そうな手触りなんです。
煮る際も、皮も割とすぐ柔らかくなります。
内袋ごと煮ても煮ているうちにきれいに溶けるのでとにかく作るのが楽。
あと、透明感のあるジャムになってくれるのもうれしい。
こんな感じで、他のマーマレードと比べても、簡単上手に作れる部類なので初めて作る方にもおすすめです。
柚子の種も活用
柚子の欠点は種が多いこと。
立派な種がたくさん入っています。
種のまわりにもペクチンが多いので、捨てずに活用します。
ちなみに昔から柚子の種とお酒を漬けた手作り化粧水なんて言うのもあるんですよ。
方法その1、洗う
種を水で洗ってその水もジャムを煮る際に活用します。
種を洗った水はかなりぬるぬるして、ペクチンが出てるなぁと感じます。
洗った水でジャムを煮ます。
方法その2、お茶パックに入れて煮る
種をお茶パックに入れて使います。
皮と袋、果汁、水を入れて鍋で煮る際に一緒に入れて煮ることで、ペクチンをとります。
お茶パックのかわりに、ガーゼ等に包んで縛っても構いません。
種を入れずに作ると、トロミがつかない?
そんなことはありません。
種以外にもペクチンがあるので、入れなくてもトロミはつきます。
圧力鍋でゆずジャム作り
圧力鍋や電気圧力鍋でマーマレード作り。
最近はもっぱらこれでやってます。
今は電気圧力鍋を使ってます
電気圧力鍋は万能調理鍋とも呼ばれるように
一台で煮こみ、スロークッカー、発酵、蒸し等便利に使えます。
炊飯に活躍、後よく作るのが、汁物、おでん、角煮、ジャムです。
手羽元もほろりと煮ることができます。
圧力鍋でジャムを作ると時短になる?メリットは?
加圧する際に、圧が上がる前、下がるまで待つ時間はかかります。
加圧せずに煮詰める時間もかかります。
加圧時間は、数分です。
トータルすると少し時短。
あと光熱費の節約になります。
長く煮ることなく、果物を柔らかくできるのも圧力鍋のメリット。
柑橘の皮を柔らかくするのも得意です。
さらに、電気圧力鍋の場合、ボタンを押せば加圧作業を勝手にやってくれるので楽できます。
最近はインスタントポットを使っています。
圧力鍋で煮つめる作業は加圧なしで
柚子マーマレードをインスタントポットで作る場合
高圧2分→ナチュラルリリース。(自然に圧が下がるまで待つ)
圧が下がればフタをあけ、皮が柔らかくなったかチェック。
2分でも柔らかくなっていました。
*電気圧力鍋によって、圧力の違いで調理時間に差があることがあります。
皮が柔らかくなった後は砂糖を加えて煮詰めます。
この作業は加圧なしで煮ます。
フタをせず、時々混ぜながら煮ます。
焦げつかないように、鍋底から混ぜます。
側面もくっつきやすいので注意。
電気圧力鍋の場合も機種によって名前は違いますが、煮込みコースがあります。
例えば、アイリスオーヤマ製の電気圧力鍋なら「鍋モード」
インスタントポットの場合は「炒め物」を選択
すると内釜が熱せられて、炒め物の他に煮込みにも使います。
炒め物の中モード。
(様子をみて、3回目の砂糖を加えたら低にしても)
圧力鍋の説明書によくある注意書き
ジャムを作る際、鍋に多くの分量(水・食材合わせて)入れて加圧しないこと
圧力鍋の深さに対して、上の方まで材料を入れると、調理の際に泡立ったり、跳ね上がった時に、部品が詰まることがあり危険なためです。
特に砂糖を多く加えるて煮ると粘度が上がり、危険度が増します
加圧せずに煮る場合は、通常の鍋と同じ扱いになります。
カレーを作る際もカレールウを入れての加圧は禁止されています。
カレーのルウを入れると汁にトロミがつくからです。
まずは野菜、水等を加圧してスープを作り
圧が下がれば、ルーを入れて圧力なしでルウを煮溶かしてとろみをつけます。
マジカルキッチン圧力鍋でジャムレシピまとめ

作りやすく上品な味わいの柚子マーマレード
圧力鍋で煮る方法も書いてます。

金柑を使った圧力鍋で作るマーマレードジャムです。
とろりと柔らかに仕上がります。

金柑について、ジャム作りの基本、保存法、マーマレードの使い道等も紹介。

りんごのさわやかさと優しさと可愛らしさをビンに詰めて。

手作りジャムの喜び
作っている時から台所に良い香りがすること。
その時にしか味わえない旬の季節の果物を瓶に詰めて。
透明感のある煮上がり、口にすればふわりとフルーツの香り。
ああ、格別の贅沢。
作ったかいがあったなぁとしみじみ思います。
保存してあった瓶をあけたときも、作った時と変わらぬみずみずしさが蘇って、またまた感激してしまうのです。
















